社外取締役インタビュー
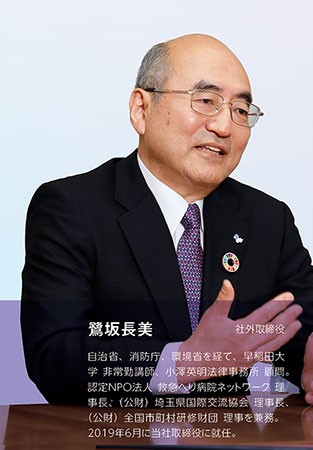
資本市場との対話を通じて信頼関係を築き、企業価値向上に向けた変革を目指す
前中期経営計画「SGH Story 2024」の振り返りと、次期計画「SGH Story 2027」の策定の議論
秋山前中期経営計画期間は、非常に厳しい事業環境だったと思います。当社グループは、業界の未来を見据え、適正運賃収受の継続、物流インフラ維持のための投資を行ってきましたが、宅配便業界の競争が激化する中で、最終的には物量を減らす結果となりました。こうした環境下での中期経営計画策定ということで、私はまず「当社グループは将来的にどのような会社になるのか」という問題提起をしました。これは、「どういう立ち位置の会社になりたいのか」について、経営陣がどう考えているのかが最も重要だと思ったからです。この問いに対して、宅配便は非常に重要だが、これに付随する部分で海外に注力する、国内でサービス領域を拡張する等、さまざまな案が出ました。そのそれぞれについて数多く議論を重ね、本中期経営計画の方向性が出来上がりました。
鷺坂前中期経営計画期間においては、新型コロナウイルスなどの影響で業績が大きく変動しました。特にグローバル物流は影響が大きく、その点を踏まえてグローバル物流の業績を個別に示す方がいいのではということを提言しました。今回、セグメントの変更を行い、グローバル物流事業を独立したセグメントとしてお示しできるようになった点は大きな進歩だと考えています。
髙岡本中期経営計画は前回策定時より、数か月早い6月頃から動き出し、社外取締役も社内取締役とともに初回の議論から参加いたしました。秋山さんもおっしゃっていたように、最初に大きな戦略や方向性の確認から始まり、昨今のECプラットフォームの動向や社会情勢、国内デリバリー事業を中心とした競争環境等を確認した上で、どこに注力すべきかについて議論を重ねました。最終的には、グローバル物流事業の本格的な育成・拡大を見据え、資本収益性の観点を取り入れたキャッシュアロケーション、事業ポートフォリオマネジメントを念頭に置き、開示を含むさまざまな点に関して社外取締役から提言しました。また、本中期経営計画では、定量的な目標を開示することにこだわり、2030年度の経営目標としてセグメント毎の営業収益や、営業利益、ROE、ROICなどを明確化しました。特に、セグメント別ROICの開示については、取締役会だけでなく、全取締役が出席して毎週実施している役員ミーティングでも活発に議論を行いました。各セグメントの収益性・成長性や今後の位置づけを対外的に開示することで、例えば、従業員から見た時に自分の所属するセグメントが注力領域ではないという懸念等が、従業員の士気に関わるのではないかという意見も出ました。最終的には、定められた期間内にハードルレートを超えないと自分たちの事業が整理対象になるという危機感にも繋がり、より高いモチベーションを持って仕事をしていただけると考え、開示に踏み切りました。
名糖運輸・ヒューテックノオリンとMorrison社のM&Aに関する議論
鷺坂当社グループがトータルロジスティクスを提供する総合物流企業を目指すにあたっては、現状少し手薄な領域を補完する成長投資を常に検討していく必要があると考えています。そうした中で、名糖運輸とヒューテックノオリンは、当社グループで機能をもっていなかったサプライチェーンの上流から中流、BtoB低温物流の領域に強みを持っており、当社グループのラストワンマイルの低温物流機能と組み合わせることで、今後はふるさと納税をはじめとする食品EC市場などの成長分野のサプライチェーン全体にアプローチが可能となります。Morrison社については半導体等ハイテク製品関連輸送を主力とし、航空輸送に強みを持つグローバルフレイトフォワーダーであり、既存のエクスポランカ社とは取扱商材や得意とする輸送レーンも異なるという点で、相互補完関係にあります。こうした観点で、この2件のM&Aは、十分なシナジーを生み出すことができ、中長期的な企業価値向上に資するものと判断しました。
秋山低温物流領域に関しては、以前から成長領域と位置付けていましたが、本格的な参入に当たっては、「当社グループの持続的な成長に資する投資か」という観点で議論を尽くしました。最終的には、現在展開しているtoCの宅配便ビジネスは名糖運輸・ヒューテックノオリンが持っていない領域であり、宅配便事業との親和性が高く、十分なシナジー効果が見込めると判断し、買収に踏み切りました。Morrison社については、エクスポランカ社と同様にフォワーダーという共通の業態であることから、業務面の連携は十分に図れると考えています。加えて、鷺坂さんもおっしゃっていたとおり、エクスポランカ社がアパレルを、Morrison社がハイテク製品関連の商材を取り扱っているというように、全く異なる顧客層を持っていることから、新たなアプローチも可能となります。人口減少が見込まれる国内市場に依存しないためにも、海外でビジネスチャンスを獲得していく国際戦略は理にかなっていると思いますが、今後はエクスポランカ社やMorrison社で持っているノウハウをいかに活用していくかが課題だと思います。
髙岡投資の目的についてはお二人に話していただいたとおりで、当社グループにとって適切な投資ができたと考えております。両社とも「本当にこれだけのシナジーが出るのか」や「この価格で資本市場から納得が得られるのか」は意思決定のプロセスの中で特に気にかけていました。取締役会だけでなく、それ以外にも非常に多くのミーティングを開いて、何度も執行側と事業計画の議論を重ね、最終的なバリュエーションを算出しました。
防災サポート財団の設立と財団に対する自己株式の第三者割当に関する議論
鷺坂当社グループは、物流インフラを支えているという点で公共性の高い事業であるという自負のもと、過去から災害時には被災地に向けて支援物資を運ぶなど社会的責任を果たすとともに、各自治体と連携協定を結び、災害発生時に迅速な支援ができる体制を整えてきました。そうした中、2024年1月の能登半島地震では、既存の災害支援体制に課題感も見えたことから、被災地からの具体的な要請を待たずに、政府が主導して必要な物資・設備を届ける「プッシュ型支援」の体制構築が求められてきました。防災サポート財団の設立は、物流を担うわれわれのような企業にとっては、社会貢献という側面だけではなく、企業としての使命を果たす取り組みだとも考えています。こうした活動が社会に認められることで、企業価値の向上にもつながるものと考え、私は設立について賛同しました。
髙岡財団の活動資金に関しては、第三者割当によって割り当てるSGホールディングス株式の配当を原資とするというのが今回のスキームですが、特に議論したことは、(1)中長期的な企業価値の向上、(2)株式の希薄化、(3)議決権の行使/不行使、の3つの論点です。
今回、財団に対して株式を1円で有利発行するにあたり、処分株数は、財団の事業計画に基づいた必要最低限の株数とするように提言しました。また、株式の希薄化を回避する観点で、希薄化率を上回る自己株式の取得を同時に行うこととしました。当然ですが、将来の利益成長に対して現時点での株価が割安との判断に基づくものです。また、公益性の高い事業内容であることからも、財団の意思決定に対する独立性や透明性を確保するために議決権を不行使とすることについても社外取締役から提言しました。
3つの論点の中でも最も重要なのは、先程鷺坂さんがおっしゃったような(1)中長期的な企業価値の向上だと考えています。印象に残っているのは、「私たちのビジネスは、国から公道というインフラを無料で使わせてもらって成り立っている」という会長・社長がおっしゃっていた言葉です。無料でインフラを利用している以上、災害等有事の際には被災地に物資を届けるのが物流インフラ企業としての責務である、という考えを聞き、当社グループが、財団の活動と一体となって、災害時においてもお客様や社会にとってのインフラであり続けることこそが、企業としての信頼性を高め、将来的なキャッシュフローの獲得や持続的な成長、そして企業価値向上につながるものであると理解しました。
秋山髙岡さんがおっしゃるとおり、中長期的な企業価値向上につながるのかというところが非常に重要なポイントだと思っています。
鷺坂さんがおっしゃったことにも通ずると思いますが、個人的には、前の会社で、阪神淡路大震災の際に、大阪から神戸のポートアイランドにバージ船で水や食料を届けたということが、強く記憶に残っています。当時は食品を扱う会社でしたが、普段消費者の皆さまに商品を買っていただいて、我々の会社が成り立っているので、有事の際には逆に市民の皆さまに物資を届けることは、義務であるという思いがありました。
災害時の支援活動は個人で行うには限界があります。だからこそ、全国規模で組織的に支援できる体制には大きな意義があると感じています。当社グループは物流を生業とする企業ですので、こうした取り組みは社会的責任を果たし、お客さまや社会からの信頼を得ることはもちろん、国や自治体に対する新たなソリューションの創出など新しいビジネスの機会にもつながるものであり、十分に、中長期的な企業価値向上につながる取り組みになると考えています。
役員報酬制度や指名・報酬諮問委員会の体制変更について
鷺坂ガバナンスを高める観点で、役員報酬制度については、企業価値向上を中心とした経営方針の一環として金融庁からも透明性のある開示が求められており、投資家の関心も高まっている事項です。そうした環境下で、役員報酬の評価指標・基準の見直しを実施し、資本収益性や株価との連動をより明確化したことは、企業ガバナンスを強化するという点で市場から求められる水準にアップデートできたと認識しています。
また、指名・報酬諮問委員会については、これまでは私と髙岡さん、そして栗和田会長の3人が委員を務め、会長が委員長を務めていました。社外取締役が過半数を占める構成のなかで、私たち2名は独立した立場から意見を述べており、これまでも委員会としては適切に機能していたと考えていますが、より独立性や客観性を高めるという観点で今回、委員長は社外取締役とすることとし、髙岡さんが委員長、委員は私と松本社長、という3名の体制に変更しました。
髙岡私も鷺坂さん同様、委員会としては適切に機能していたと考えています。ただ、社外取締役が委員長を務めることで、少数株主の視点に立ったガバナンス強化の姿勢を明確に示すことができると考え、今回委員長を拝命しました。
報酬制度については、今回から基本報酬にROEやTSRとの連動性を明示しました。これは、利益が出ていても株価が上がらないケースもあるため、株主と目線を合わせるという観点ではTSRを報酬に反映させることが重要であるとの考えからです。取締役が株主と同じ目線で経営に取り組んでいることが、より明確に伝わるようになったと思います。加えて、開示においても伝わりやすい明瞭な表現を意識し見直しました。以前は「固定報酬」と「業績連動型株式報酬」と記載していました。このため、実際は、固定報酬には業績連動の要素も含まれており、前年度の業績を考慮して翌年度の報酬水準が決まっていたにも関わらず、役員報酬があまり業績と連動していないように見えていたと思います。よりわかりやすくご説明するために今回から固定報酬を「基本報酬」という記載に変更しました。実は、開示の表現に課題があったと気付くきっかけになったのは、2025年4月に実施したスモールミーティングにおける「役員報酬における業績連動比率が低いのでは」という機関投資家からの声でした。こうした投資家との対話等も活用しながら、今後も必要な改善を行っていきたいと思います。
秋山今回、役員報酬制度を見直す中で、すべてのステークホルダーに対して、企業の取り組みや考えをわかりやすく伝えるための表現が重要だと再認識しました。その意味で、IRは今後ますます重要になっていくと感じており、私たち社外取締役を含めてIR活動を通じて信頼関係を築いていくことが、企業価値の向上にもつながると考えています。
髙岡現在、日本の金利は上昇局面にあり、今後、負債コスト・株主資本コストの加重平均である資本コストも相応に上昇するものと思います。当社グループでは、稼ぐ力を高めると同時に資本コストについても厳格に管理しています。そういった観点で、ここ数年は資本コスト低減のため、金融機関からの調達を活用して投資し成長を目指すという、いわゆるレバレッジ経営を行っており、足元の当社の負債比率は、名糖運輸・ヒューテックノオリンとMorrison社への大型投資により上昇していますが、負債比率が高まることで、今度は財務体質への懸念から負債コストが上昇する可能性もあるため、バランスを見ながら、資本コストを適切にコントロールし、着実にそれ以上のROICを生み出していきます。
また、株主資本コストの観点では、計算に含まれるベータ値は、企業が唯一コントロールできる要素です。ベータ値を下げるためには、投資に伴う負債のコントロールに加えて、投資家が当社グループに求めていることを把握し、情報の非対称性を極小化することが重要であり、そのためには資本市場との対話が大切です。今期は先ほどもお話に出ましたが、社外取締役3名と機関投資家とのスモールミーティングも実施しました。特に、今回のような大型M&Aによる成果及び、実現のプロセスは対話の中で着実に示していく必要がありますし、それを社外取締役が監督していることを市場にお伝えすることが信頼関係の構築につながると思います。さらに、株価についていうと、プライム市場の上場企業のPER平均が16~17倍であることに鑑みれば、当社は今日(取材時)のPERで17倍程度なので、足元の株価は標準的な水準であると言えますが、過去の当社のPER水準からすると改善の余地があると考えています。PER、ひいては株価を上昇させるためには、EPSをしっかりと上げていくことに加え、将来への期待感を持っていただくことが重要です。そのためには、資本市場ときちんと対話をして、私たちの投資の姿勢や着実にリターンが出ていることなどを示していく必要があると考えています。
秋山今までも経営・財務戦略をお伝えする機会はあったものの、収益が安定的に伸びていた中では、成果をしっかりと出すことに重きが置かれていた部分もあるのかもしれません。しかし、昨年から今年にかけて、我々社外取締役も含めて、経営陣全体が資本市場との対話をしっかりとやっていくという思いをより強くし、中期経営計画にも資本市場との対話強化を明記しました。「何をやっているのかわからない会社」と思われてしまっては、それだけで信頼を失う可能性があります。ですから、これまで以上にオープンに情報を開示し、企業としての中身をしっかり伝えていく必要があると感じています。
鷺坂髙岡さん、秋山さんからもありましたが、これだけの大型M&Aが続いた状況ですので、市場に対して丁寧に説明するなど、積極的にコミュニケーションを取っていくことが重要であり、これに尽きると思います。
脱炭素への取り組みについて
鷺坂脱炭素の取り組みに関して、当社グループは京都に本社を構えていることもあり、京都議定書が採択された1997年頃から環境への意識が高く、積極的に取り組んできたと認識しています。特に当初は大気汚染対策として、天然ガス車の導入を積極的に進めており、外部から見ても、非常に先進的で素晴らしい取り組みだったと思います。
現在、社内ではサステナビリティ委員会を設置し、さまざまな議論を重ねながら、政府の方針に沿った形で着実に取り組みを進めています。日本では「GX推進法」が施行されており、2025年2月には「GX2040ビジョン」も閣議決定されました。今後もその計画に基づいて、グループ全体で対応していく方針です。こうした環境問題への対応は、社会貢献的な側面のみならず、企業としての社会的責任であり、持続可能な会社経営を行っていく上では重要課題であると認識しています。
髙岡当社グループのように大量のエネルギーを使う物流企業にとって、輸送においてどのエネルギーを選ぶかは非常に重要な課題です。現在、EV(電気自動車)やFCV(水素を使った燃料電池自動車)などの開発が進んでおり、当社グループにおいても一部導入を行っていますが、燃料効率やコスト面等の懸念から、積極的な導入には課題も残されています。このほか、バイオディーゼル車などさまざまな選択肢が考えられる中で、当社を含む物流各社は、環境負荷低減と経済合理性の両立を目指し、どのエネルギーをどのようなバランスで活用するべきかを真剣に見極める局面にあると思います。
秋山当社グループは天然ガスの導入こそとても早かったのですが、髙岡さんも触れられたように、EVの導入は他社の方が進んでいるという状況にあります。ある意味、流行に飛びつくのではなく、環境対応車の開発状況もしっかりと一歩引いて、本当に効果的かどうかを慎重に見極める部分があると思っており、その点は非常に評価しています。いつ、どういう技術が開発されても、対応できる体制さえ作っておけばいいと思い、そうした体制を整えている会社だとも感じています。
鷺坂加えて、協力会社あっての当社グループの物流インフラだと思っています。仮にすべてをEVに切り替えれば、協力会社にもコスト面で大きな負担がかかります。いわゆる「スコープ3」である取引先を含めた脱炭素の取り組みが求められており、協力会社との連携や支援策も含めて考えていく必要があります。
鷺坂中期経営計画でもお示ししているところではありますが、デリバリー事業に関してはこれからの成長分野として、インバウンド等、観光需要をにらんだリアルコマースといった新領域、さらに低温物流、越境ECに注力していくことが、目標を着実に達成するための重要なポイントだと考えています。
加えて、2025年3月期には2件の大型M&Aを実施していますので、今期は、当初想定していたシナジー効果を、定量・定性の両面で具体的な成果として示していくことが求められます。また、繰り返しになりますが、シナジー創出に向けた取り組みなどは、資本市場の皆さまに対して、説明を尽くしていかなければならないと考えています。
髙岡鷺坂さんがおっしゃることに集約されていると思います。今回の中期経営計画を通じて、社内全体でミッションと目標が明確になったと感じています。国内デリバリー事業では、越境ECやインバウンド対応の強化、適正運賃の収受による収益力向上が重要です。また、ロジスティクス事業では、名糖運輸・ヒューテックノオリンとのシナジー創出に向けた取り組みの推進、グローバル物流事業では、Morrison社のPMIを推進するとともに、既存のエクスポランカ社とのシナジー創出により、安定した収益基盤の確立が求められています。こうした各セグメントの成長戦略を着実に実行することで、目標達成に向けた成果が期待できると考えています。
秋山短期的なモニタリングや実行も重要ですが、それ以上に「この会社が将来どのような姿になっていくのか」といった長期的な成長ビジョンを、従業員全員がしっかりと意識して業務に取り組むことが大切だと感じています。
当社グループは「宅配便だけの会社」ではなく、トータルロジスティクスを提供できる総合物流企業への道を歩んでいます。もちろんコア事業である宅配便でもしっかりと収益を出していく必要がありますが、今後は国内だけでなく海外との連携もますます増えていきます。そうした変革の中で、他社に負けないサービスを提供していくのだと、従業員の皆さんが一層意識を変えていくことも非常に重要だと思います。こうした意識で、今年1年間しっかりと取り組むことで、2030年度に向けたありたい姿がより明確に見えてくるのではないかと期待しています。




