社外取締役インタビュー 秋山取締役
秋山真人
社外取締役
(株)ニチレイ、(株)ニチレイロジグループ本社、(株)ロジスティクス・ネットワーク、東京団地冷蔵㈱で勤務。東京冷蔵倉庫協会、(一社)日本冷蔵倉庫協会を経て、2020年6月に当社取締役に就任。
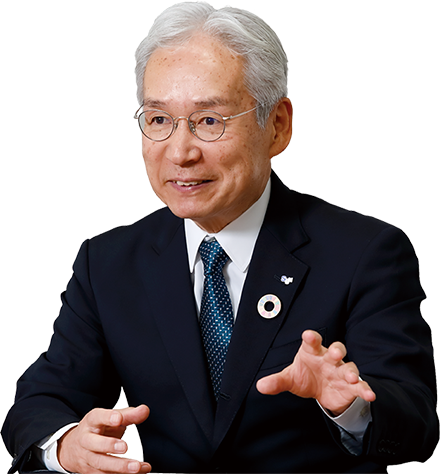
秋山取締役にお伺いします。
当社の海外事業戦略に対するお考えをお聞かせください。
当社グループは2030ビジョンにおいて、宅配便以外の成長の軸として国際事業の強化を掲げています。エクスポランカ社はその中核を担う存在であり、コロナ禍においては世界的にサプライチェーンが混乱する中でも、顧客ニーズに応えてスペースを確保したことで急成長しました。ここ1~2年は、物量の減少と運賃の低下、物量に合わせたコストコントロールに苦しんでいますが、2030ビジョンの実現に向けては、エクスポランカ社を再び成長軌道に乗せることが重要となります。
エクスポランカ社の立て直しにおいて、まず必要なのは、グループのコアビジネスである宅配便とのシナジーをこれまで以上に発揮できる体制を築くこと。次に、現状の取引について採算を重視してあらためて精査すること。最後に、コロナ禍で増強した拠点や従業員を適材適所に配置することです。シナジーの創出に向けた取り組みや拠点・従業員の再配置など、進捗しているものもあると認識しておりますが、これらの取り組みはまだ道半ばです。2025年3月期での成果および、次期中期経営計画や2030ビジョンを見据えたこれからの国際戦略に注視しています。
また、松本社長は、SGホールディングスがエクスポランカ社をバックアップすると明言し、社長直下に国際事業の専門部署を新設するとともに、エクスポランカ社の非上場化に着手するなど、組織体制の変革を進めています。私自身の経験に照らしてみても、買収した企業のマネジメントにおいては責任の所在を明らかにし、本社サイドからもしっかりとバックアップすることが非常に大切だという実感があり、日本からの支援体制の構築は評価できます。これらの取り組みを通じて、エクスポランカ社が再び成長軌道に乗ることを期待しています。
2024年問題に対する課題認識について教えてください。
2024年問題を受けた直接的な課題としては、トラックドライバーの時間外労働時間の上限規制により、特に中小規模のパートナー企業は人手不足の加速が見込まれる点です。このような状況の中で、まずは当社が率先してパートナー企業との連携を強固なものとし、リソースを共有できるような体制を構築するなどして、人手不足を克服する取り組みを業界全体に波及させていかなければ、物流そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。そのための手段として、必要であれば資本投資を行うことも選択肢としてあってもいいと私は思っています。パートナー企業との連携強化に関しては、以前から多くの施策が検討されており、進捗については非常に注目しています。
2024年問題に関連するもう1つの課題は、荷主から頂いている運賃がまだまだ低い水準にある点です。物流を維持するためには現状の運賃では不足しており、適正な運賃を頂く必要があるということをこれまで以上に強くお伝えしていく必要があります。こうした適正運賃収受の取り組みは、物流を支えるパートナー企業の皆さんが事業を継続するという観点で、元請企業が責任をもって果たすべき使命でもあります。また、これは少し実務的な話になりますが、人手不足への対応として、大手EC事業者のようにインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負っていただくといった、これまでの物流事業者とは違ったアイディアで配達人員を確保することも手段の一つとして考えられます。これはあくまで例として、ということではありますが、今後の持続可能な物流の在り方を考えるうえでは、異業種の取り組みについても積極的に研究し吸収するような柔軟な姿勢も持つべきです。前述した適正運賃収受の進展や新たな手法による配達人員の確保など、2024年問題が物流の事業環境の変化を促進している側面もあり、そういう意味で2024年問題は変革のチャンスとも捉えています。
当社の人材育成に関してどのように評価されていますか?
人材育成を考えるうえで大切な論点となるのは、人材を「コスト」として見るか、「資産」として見るかだと思います。物流業界における人材は、どちらかというとコストとして見られる側面が強いです。そのような環境の中、当社グループが早くから力を入れて人材を活かす取り組みを行っていることは認識しています。例えば、私がまだ㈱ニチレイロジグループ本社にいたときにSGホールディングスに女性活躍推進の取り組みについて、いろいろと教えていただいたこともあります。ですが、こうした先進的な取り組みを行う企業であり続けるためには、人材を「資産」として捉えることができるような人材育成を、今以上に意識的に行うべきです。具体的には、知識を習得するための研修だけではなく、個々人のコミュニケーション能力を最大限に高めるトレーニングが必要だと感じています。ここでいうコミュニケーション能力とは主に「聞く力」です。これは管理職において重要であるのは勿論ですが、パートナー社員やパートナー企業などと日常的に接する現場の従業員にこそ必要なスキルでもあります。日々の業務の中で、従業員一人一人が聞く力を持って対峙すれば、自ずと活発な議論に発展し、こうした積み重ねがフラットな企業風土を醸成することにつながるとともに、人材が「資産」として機能すると考えています。
加えて、国際戦略を推進するうえでは、海外の事業会社との人材交流も進めていくべきだと思います。現状、当社グループにおいては、海外への派遣や日本国内への受け入れは言語の壁から限定的になっていますが、国境を超えた交流が活発にできるようになれば、ビジネスの幅も広がります。そういった人材が、将来の幹部、役員の候補となっていけば、持続的な成長を推進してくれる存在になると期待しています。
資本コストや株価を意識した経営が求められる中、足元の株式市場からの評価についてどう捉えていますか?
当社の株価は、主に2024年3月期決算やC&Fロジホールディングス(以下、C&F)のTOBを開示したタイミングで下落しました。中でもインパクトが大きかったのは、C&FのTOBです。報道を見てもTOB価格は妥当なのか、シナジーは創出できるのか、などの論点について疑問符がついて報じられており、このことが資本市場の不安につながり、結果的に株価へ大きく影響が出たものと推測しております。
私自身、社外取締役として機関投資家の方との1on1のミーティングで直接コミュニケーションをとらせていただくこともありますし、役員ミーティング(社外取締役を含むSGホールディングスの取締役全員および常勤監査役が出席する定例会議)においても、機関投資家の皆さまから寄せられるご意見について共有を受けています。そのご意見をお伺いする中で私が課題に感じているのは、資本市場との対話をさらに充実させる必要があるという点です。今回のC&FのTOBに関しては、取締役会の前段で投資案件の審議を行う「投資検討委員会」において、本件の意義やシナジー効果・投資リターン、バリュエーションの妥当性など総合的に議論を行ったうえで、TOBを進める方向で承認され、取締役会にて決議されております。このような過程を経て当社として認識した投資効果やその進捗状況については、定性・定量両面で、今後も継続して皆さまにご説明すべきです。これは余談ですが、当社の社外取締役に着任した当初、各投資案件の判断においてしっかりと投資リターンを計算し、意思決定を行っている点について非常に驚いたことをよく覚えています。事業別にWACCを上回る収益性を意識することは勿論ですが、将来あるべき事業のポートフォリオや資本コストを意識していくことが、より必要になるものと思っています。併せて、これら将来あるべき姿を資本市場の皆さまにマネジメント自ら積極的に説明するべきだと思っています。




