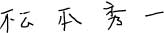トップメッセージ
統合報告書2025より抜粋
前中期経営計画「SGH Story 2024」を、どのように振り返るか。
成長への布石を打った前中期経営計画の3年間
前中期経営計画「SGH Story 2024」(2023年3月期~2025年3月期)を振り返ると、当初の想定をはるかに上回る外部環境の変化に対し、打ち出した各種諸施策への効果は道半ばのものがある一方で、将来の成長への布石を打てた3カ年でもありました。
私は、前中期経営計画の途中から社長に就任いたしましたが、就任直後である2023年3月期の第2四半期以降、事業環境の変化等によりデリバリー事業の取扱個数が下がり始め、またグローバル物流事業の業績もコロナ禍の特需反動等、苦戦を強いられました。そのような状況下であったため、先ずは現状をしっかり把握、認識し、課題に対する対応策の実施を最優先で行いました。
最初に着手したことは、物流インフラの維持に向けたリソースの確保、営業推進体制の変更、株主還元の考え方の整理の3つです。2024年問題対応の本格化や急速なインフレ環境への転換の中において、当社の事業を担う人材の流出を防ぎ、物流インフラを維持することでした。そのために当社グループの従業員やパートナー企業の皆さまの労働環境や待遇改善は特に重点的に取り組みました。この点は迅速に対応し、一定の効果が発現できたと評価しています。
アフターコロナや激動する国際情勢、国内宅配便業界の競争環境激化といった目まぐるしく、また大きく変化する事業環境に伴い多様化・高度化するお客さまの物流ニーズをこれまで以上に素早くキャッチし、戦略に反映させていくことは継続的な課題であると認識しております。それに対応するため、グループ全体の最適を考えた営業推進体制の改善にも着手いたしました。ソリューションの起点となる、お客さまの情報を集約する取り組みを加速させ、営業部隊や現場がグループを横断し連携を取りやすい体制構築を目指しています。
株主還元の考え方についても整理を行いました。当社は新しい中期経営計画の公表の際に配当方針として累進配当や自己株式の機動的な取得を掲げ、3カ年累計の総還元性向を60%以上と定めました。着実な株主還元を継続することで、株主の皆さまとの長期的な信頼関係を構築してまいります。
前中期経営計画の期間中は厳しい事業環境にあったからこそ、足元の環境だけでなく中長期的な外部環境の変化を見据えた意思決定にもつながりました。「SGHビジョン2030」で掲げるトータルロジスティクス提供へ向けた基盤強化として名糖運輸・ヒューテックノオリンとMorrison社のグループ入りを実現したことは今後の成長に向けた布石を打つことができたと評価しております。2社をグループ化した背景には、日本は将来的な人口減少が避けられず、また、GDPの大幅拡大が見込めない中、ドメスティックな宅配便に依存した事業を展開するだけでは、今後当社が大きく成長するために不十分であるという考えがあります。宅配便需要のみを見れば、今後もEC化率の上昇等を追い風に緩やかに増加する見通しですが、ラストワンマイルの輸送は特にプレイヤーも多く、競争が過熱している状況に変わりはありません。その中で他社との差別化を図るには、当社グループの強みである宅配便を起点にサプライチェーンの川上へ、総合的にサービスを提供できる物流事業者、すなわちトータルロジスティクスを提供できる物流パートナーになる必要があると考えます。そのためには、既存の顧客・事業基盤をもとにソリューション提案の高度化を進めるとともに、成長が見込まれる領域で新たな顧客・事業基盤の獲得が必要であり、これを確保する手段としてM&Aを選択しました。名糖運輸・ヒューテックノオリンは低温物流、Morrison社はハイテク・半導体関連物流と、いずれもこれまでの当社リソースには不足があるものの今後成長が見込まれる領域に強みを持つ会社であり、まさに当社グループのトータルロジスティクスの戦略に合致する領域を主戦場にしています。彼らとは必ず良いシナジーを創出できると考えており、このM&Aによって目指すべきトータルロジスティクスの提供の実現へ近づくことができたと考えています。
SGHビジョン2030の達成に、どのような姿勢で向き合うか。
今回、長期ビジョン「Grow the new Story. 新しい物流で、新しい社会を、共に育む。」をより平易な言葉で、ありたい姿として「お客さまおよび社会において、必要不可欠な存在(=インフラ)であり続ける」と再定義しました。“インフラであり続ける”という言葉の背景にあるのは、物流企業としての使命感です。人々が生活していくためには、食料をはじめ不可欠な物資があります。現代社会においてそれらを自力で得ることは多くの人にとって困難であり、誰かが生産者から人々のもとへと届ける必要があります。当社グループはその届ける役割を担っており、平時はもちろん、災害等の有事においても止めることなく“あり続けること”が大前提です。
これらの想いを胸に、私たちは社会にとってインフラであるという自負を持ち事業活動を行うことを今回のありたい姿で示しており、同時に当社の持続的成長への源泉となっています。
お客さまのニーズに合わせたトータルロジスティクスの構築
“インフラであり続ける”ために当社グループが創出すべき価値とは、トータルロジスティクスの提供です。私たちが目指すトータルロジスティクスとは、お客さまの小さなニーズも見逃さず、潜在的な課題も拾い上げ、解決する物流を提供することです。すなわち、確実に荷物をお届けすることを中核に、運び方やその前後の物流機能までも網羅した利便性の高いソリューションを提供するということです。例えば宅配便に限っても、荷物のサイズなどに応じて利用する事業者を使い分けているお客さまが多いと思いますが、実際には手間であるはずです。ポスト投函、宅配便、低温、重量物、特殊輸送、海外まで、物を運ぶ全ての手段をSGホールディングスグループがトータルで提供することで、お客さまから必要とされ続ける存在となり、さらにはお客さまの先にいる消費者、ひいては社会にとっても必要なインフラへと成長できると考えています。
お客さまのニーズに合わせ、配送方法をカスタマイズするのは、当社グループが創業当初から「飛脚の精神(こころ)」として実践し続けてきた得意領域です。長年にわたり培ったノウハウを、幅広い事業領域に水平展開することで、トータルロジスティクスを実現できると確信しています。
これまでも宅配便事業を基盤に、国内外で顧客基盤・事業基盤を拡げてきましたが、得意とする物流領域には未だ濃淡があり、対応できるニーズも一部という認識です。事業・機能ごとにお客さまのニーズをさらに深掘りしながら、川上から川下へ広がる物流ソリューションを統合していく。それにより、サプライチェーン全体を管理することが、今後の事業成長にとって重要となります。
成長戦略をスムーズに進めていくために、私は社長として、各事業の管理監督・執行はもちろんですが、この計画の実現に向けて何をするのかを自分の言葉で直接各グループ会社のトップへ伝え、グループ全体でビジョンを共有することが重要であると考えています。そのため、私は社長就任以来、グループ間での情報交換の場を毎月複数回のペースで設けてきました。
そうしたコミュニケーションの中でのディスカッション等も踏まえて、新しい中期経営計画の発表の際に、2030年度の経営目標を詳細化し、セグメント別の経営目標とそれに紐づく戦略を設定し、対外的にも当社グループの全従業員に対してもどこを目指して何をしていくのかをわかりやすくすることを意識しました。達成に向けては各社の主体性を尊重しながらも、きめ細かな対話の中で理解を深め合い、責任分担ができる体制を構築していきます。
新中期経営計画「SGH Story 2027」の重点戦略と実現に向けて特に重要な課題とは
新中期経営計画「SGH Story 2027」の重点戦略
今年度からスタートした「SGH Story 2027」は、「SGHビジョン2030」に向けたセカンドステージであり、前中期経営計画で着手した施策を元に、投資効果の創出を図っていく3年間と位置付けています。
基本方針となるのは、「トータルロジスティクスの高度化とグローバル物流の基盤拡大」です。その実現に向けて9つの重点戦略を設定しました。

事業活動においては、宅配便をはじめとするデリバリー事業の安定成長を起点に、名糖運輸、ヒューテックノオリンのグループ化による低温物流領域の強化、Morrison社のグループ化によるグローバル物流事業の基盤強化など、事業範囲の拡大を目指していきます。また、国内ロジスティクスの付加価値向上とTMS事業領域の拡大などを通じ、中期経営計画の目標達成に向けて、取り組みを加速します。そして、それらを下支えするサステナビリティへの対応、グループ内のガバナンスの高度化の推進も引き続き進めていきます。
これらの中でも特に重要な論点は、海外事業の展開、人材の確保・活用、社会・環境課題の解決の3つです。
海外の基盤拡大と国内とのシナジーによるトータルロジスティクスの提供
「SGH Story 2027」で注力すべき事業課題はグローバル事業の基盤拡大です。世界を見渡すと、日本の宅配便業界は極めて特殊です。日本の宅配便は対面での配達が基本であり、追加料金を払わずとも1日2日で届く、希望する配達時間を指定できる等、きめ細かなサービスを安価に利用できる点が特徴ですが、このような日本式の宅配便のサービスが、例えばアメリカでも同じように求められているかというと、そうではない、という状況がこれまで続いています。このため、現段階では各国で異なる商習慣に適した方法で事業を展開していくことが重要です。現地法人のトップには現地人材を登用するなど、商習慣や文化が事業の障壁にならない体制を築きながら事業拡大を図るとともに、ガバナンスに関してはSGホールディングスグループの一員として日本と同じ水準で遵守してもらう考えで展開しています。なお、最近、アメリカの現地法人には、日本と同じサービスの展開を考えていないか等の問い合わせが届くようになりました。各国が超少子高齢社会を迎える中で、日本式の宅配便に関しても、徐々にニーズが高まってくる可能性もありますので、国内事業のサービス品質を高める等、いつでもラストワンマイルサービスが展開できる準備も必要だと考えています。

また、海外で事業を行う際にも、日系企業に知名度がある佐川急便のブランド力も営業に生かすことができます。
他方、佐川急便というとやはり宅配便が代表的なサービスであり、フォワーディングなど国際輸送のノウハウが乏しいことは事実です。鍵を握るのはM&Aで取得した各社であり、Morrison社とエクスポランカ社と連携し、フォワーディング領域から海外事業を拡大していくことです。そして、ターゲットと定める生産・消費国での3PLなどを強化しながら、販売物流領域全体にカバーする領域を広げていく。ここに、トータルロジスティクスが持つ最大のポテンシャルがあります。
働きやすい環境とモチベーションの醸成が人材確保の鍵
労働集約型の産業である物流において、人は必要不可欠です。ドライバーだけでなく、倉庫や中継センターの作業者を含め、現場の方々が「働きたい」「働きやすい」と思える環境を整え、より良い労働環境と賃金の改善を最優先すべきだと考えます。
当社グループを取り巻く日本の物流業界は、2024年問題を契機に大転換期を迎えています。トラックドライバーの時間外労働が年間960時間が上限となる等労働環境の改善につながることが期待される半面、事業構造や仕事の進め方を大きく変える必要があり、解決へ向けては業務の効率性を高め、真に必要な領域にリソースを集中させることが不可欠です。当社グループとしては、“物を届ける”という私たちの本質的業務に注力するために、例えば、荷物をトラックへ積み込む作業をAI搭載の荷積みロボットへ置き換える実験を行う等、先端テクノロジーへの投資も進めていきます。また、自社単独の取り組みだけでなく、物流業界全体の連携、社会全体のマインド醸成も必要です。例えば、一つ一つの荷物のお届け期間が、緊急性によって区分けされれば、急ぎではない物を拠点に集積し、一定量になったところで配達することで、トラックの積載率を高めることができます。
賃金改善の観点では、インフレの進行により実質賃金が目減りし、家計消費支出も絞られる状況ですが、物流事業者もコスト増に直面しており、一定の負担はお客さまと分かち合わなければ、業界全体で人材の流出が進み、荷物が運べなくなる事態は一層悪化する可能性もあります。
こうした物流業界の課題意識をお客さまや社会と共有し、全体最適を図るとともに、産業としての物流の魅力を、より高めていかなければなりません。そのためには政府・自治体との協調も欠かせず、企業や業界の垣根を超えたアプローチをすべきだと考えています。
一方で、中長期的に考えると、多様な人材が活躍するためには、単に労働条件を向上させることだけでなく、会社への帰属意識やモチベーションも重要です。例えば、評価基準も適正化すべきであり、男性中心であった物流現場のマインドを変えていくことも必要です。ダイバーシティに関する社内学習や研修を旗振りに女性や若手、外国籍の方々の活躍が、正当に評価される仕組みを構築していきます。社員のエンゲージメント調査の計測も、給与や福利厚生などの単一的な施策で結果を改善させるのではなく、やりがいや成果と連動するように、分析方法を精緻化すべきです。
防災・被災支援の中で培ってきたノウハウを社会に還元する
SGホールディングスグループが“インフラであり続ける”ために、事業活動を通じて社会・環境課題を解決することも不可欠です。当社グループが提供する価値として、トータルロジスティクスを重視していますが、これは社会・環境課題の解決にも貢献できます。例えば、資源のリサイクルやリユースなどを可能にする静脈物流の構築、車両や施設のCO2排出量など、持続的な社会の実現に向けて、カーボンニュートラルの実現に取り組んでいきます。
とりわけ、災害が頻発する日本において防災という社会課題を解決するという観点で、2025年3月に「一般財団法人SGH防災サポート財団」を設立しました。政府と一体となって防災事業を行う同財団は、被災地・避難所への迅速な物資配送を実現するため、倉庫の用意、各種支援物資の備蓄、搬入関連資機材の保有・管理など当社グループの物流ノウハウを活用しながら、政府・自治体や民間企業ではこれまで行き届かなかった領域の支援に取り組みます。
振り返ると、当社グループの災害支援活動は阪神・淡路大震災から始まりました。地震発生後、新神戸駅のガード下をお借りして物流の拠点を作り、当時所有していたヘリコプターを使って通れそうな道を探し、従業員が被災者の皆さまを訪ね歩いて支援物資の確認・輸送を行いました。こうした活動においては日頃の営業活動の中で培ってきた、お客さまのニーズを吸収するためのノウハウが実践されていたと思います。これ以降、東日本大震災や熊本地震、直近の能登半島地震など、継続的な災害支援を行ってまいりました。こうした取り組みにより、被災地の方の中には「佐川ファン」になっていただいた方も少なくないと聞いています。これまで、ボランタリーな支援を行ったり、あるいは政府・自治体の要請を受けて輸送にまつわる業務をお手伝いさせていただいたりと、災害支援活動を続けてきましたが、その中で培った災害対応のノウハウをこれまでは対応しきれなかった領域まで広げ次なる有事に備えていくことが、財団設立に至った想いです。いつ起こるかわからない災害に備え、財団が安定的・永続的に活動を行うため、当社株式を第三者割当処分により財団に割当てし、その配当を活動原資に充てることとしました。これは、寄付よりも、短期業績に左右される懸念が少なく、財団の活動趣旨に照らして適切な財源となると考えたためです。当社グループは、物流事業を営む会社として、国や自治体が整備する公道を無償で使わせていただいて事業を行っており、大切なステークホルダーとして緊急時にこそ国や自治体に恩返しをしたいという想いも強く持っています。有事においても物流機能を維持し、社会的責任を果たすことは、お客さまや社会にとって必要不可欠なインフラであり続ける、というありたい姿を体現するものであり、そうしてお客さまや社会から信頼を得ることが、持続的成長・企業価値向上に繋がると考えています。
SGホールディングスの持続的な企業価値向上へ向けて
資本コストと株価を意識した経営を実現し、さらなる成長へ
今回の中期経営計画の発表会の際に、これまで繰り返し言及した「ありたい姿の実現」に加え、「企業価値と株価の向上」も、私自身が皆さまにお伝えしたい重要なテーマとして掲げました。2030年に向け、デリバリー事業における中継センターへの施設投資や2社のM&A等、成長投資効果を確実に創出し、生み出されたキャッシュをしっかりと株主還元や次の成長投資へ結びつけ、企業価値・株価を向上してまいります。
目標としては2030年度のROE水準15%を掲げました。セグメントごとの資本収益性を高めながら、トータルロジスティクスの提供により事業成長を図るとともに、適切な財務戦略をとることで、ROEの向上を実現してまいります。
大型の成長投資については、2025年3月期に実施した2社のM&Aで一段落と考えています。資金としてはこの中期経営計画期間中に出ていくものもありますが、早期の効果発現に向けて取り組んでまいります。また、冒頭でも触れましたが、株主の皆さまへの還元については、配当について累進配当の方針を明確化し、新たに総還元性向の目線も導入するなど、過去よりも充実させました。
また、企業価値向上に向けて、株主資本コストの低減も重要です。経営の透明性の観点で、中期経営計画の重点戦略の中でもガバナンスの高度化を掲げていますが、資本市場との対話も踏まえ、指名・報酬諮問委員会のメンバー構成等の見直しや、取締役の報酬決定にROEやTSRの基準を導入するなど、株主の皆様とも目線を合わせたガバナンスの高度化に着手しています。今後も、当社の現在と未来について、より深く理解し、成長への安心感を抱いていただけるコミュニケーションについて、私自身直接対話する機会を設けるなど、重視して取り組んでまいります。
資本市場の皆さまはもちろんのこと、お客さまや、取引先、従業員、パートナー企業の皆さまに対しても、引き続き対話や情報開示などを通じて当社の持続的な成長をご理解いただき、共に成長していけるような関係性を築いていきたく思います。
私たちの創業の原点である「飛脚の精神(こころ)」とは、お客さまのために何ができるかを常に考え、誠心誠意尽くす心を指します。今後も全てのステークホルダーの皆さまの期待に応えられるよう、持続可能な成長、企業価値の向上に尽力してまいります。
2025年9月26日
SGホールディングス株式会社
代表取締役社長